2018年10月30日法(通称「農業食品法」)の適用により、2022年1月1日から、以下のように定められました。フランスの学校給食で提供される食材のうち少なくとも50%は持続可能な農法で栽培されたものではなりません。一部の学校ではさらに進んで、100%ビオのメニューを採用し、地元地域で収穫されたものを多く提供するようになっています。これは大きな一歩です。
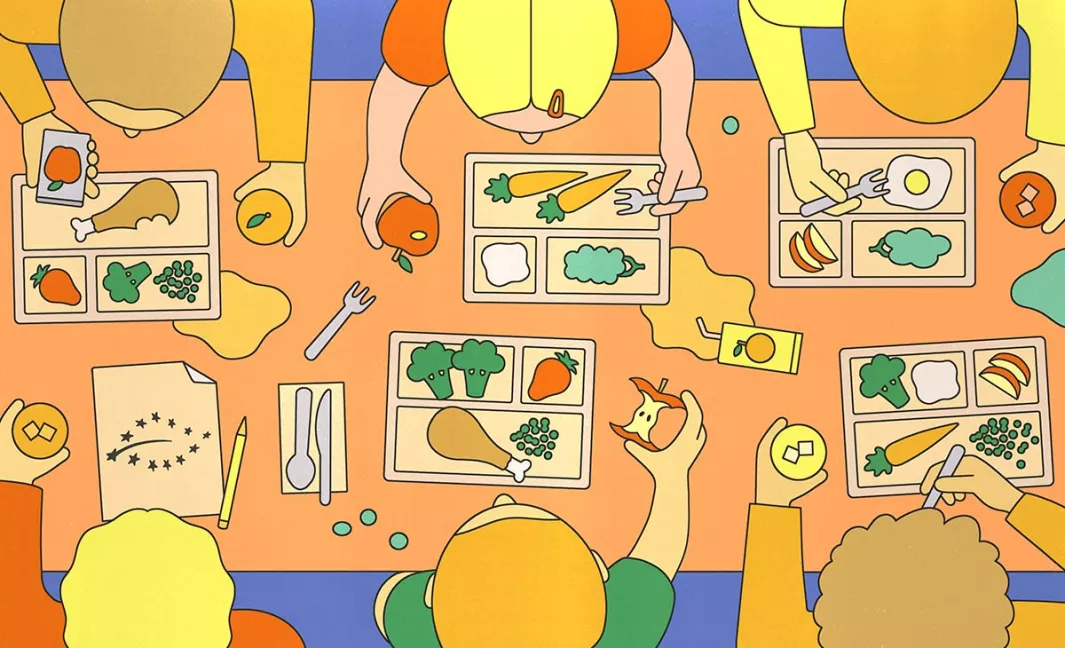
フランス南部、カマルグ自然公園の中心に位置するドメーヌ・デュ・ポッシブル校の子どもたちが毎日正午に楽しむのはシェフによって考案されたランチです。食材は学校の栽培チームが収穫したものを使っています。テーブルに並ぶ卵も、このドメーヌで飼育している鶏が生んだものです。この私立学校はジャン=ポール・キャピターニと元文化大臣のフランソワーズ・ニッセンにより設立され、食文化の継承も教育プログラムの不可欠な一部となっています。その他の公立校でも、だいぶ前からビオの食材と「ショートフードサプライチェーン(SFSCs・短絡流通)」を特徴とする食事を提供してきました。2004年以降、ブルターニュの小さな村ラングエでは、ヴェルミチェッリ入りのスープからキャラメルプリン、鶏のササミのクリーム煮、野菜のポワレまで、地域の子どもたちに提供される食材の100%がビオです。
これらの例は特別ではありません。2018年10月30日法の適用により、2022年1月1日から、フランスの学校給食で提供される食材のうち少なくとも50%は持続可能な農法で栽培された高品質なものでなければならず、そのうちの20%が有機農法で生産されたものでなければなりません。また週に1度はベジタリアンメニューの提供が必須です。将来世代の食糧問題は今後何年にもわたる問題ですから、これは注目すべき前進です。しかしタイトな予算をやりくりしながらビオ食材に移行するにはどうすればいいのでしょうか?大事なポイントは供給体制にあります。ラングエでは、自治体が地元農家のグループに発注し、毎日学校の食堂に新鮮な野菜を届けてもらっています。
ドメーヌ・デュ・ポッシブル校では、近隣のヤギの酪農家エマニュエル・ラファイエが定期的にヤギのヨーグルトを学校の厨房に配達にきます。「私たちは長期的なパートナーシップを結んでいます。羊肉が余った時はポッシブル校に安く卸すこともあります。私の子どもたちもここに通っているんですよ。子どもたちがビオで健康的な食品を食べていると知ることほど嬉しいものはありません。彼らはよりエコロジカルな道を前進させる将来の世代ですから」
価格を維持するため、供給以外にも工夫がされています。食品ロスの削減も重要です。少量を提供し、自分たちの食欲に折り合いをつけることを子どもたちに教えたり、これから数年後に100%ビオ食材に移行することを見据えて、ベジタリアンメニューを優先したりすることも次なる手段になります。
これらの前向きな進化はヨーロッパの他の国々でも見られます。イタリアでは1986年に同様の取り組みがスタートしました。ドイツでは1993年に大学に食堂ができ始め、アジャンス・ビオ(有機農業開発促進機関)によると、今日では大部分の大学でビオ食材が使われています。スウェーデンでは2013年に学校給食で提供された食材の平均23%がビオ食材でした。未来は明るいのです。
Contributor

Editor













